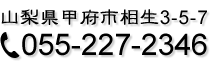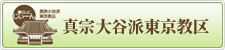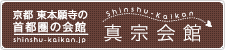現代の死生観を見直す
2009.04.28
2009年4月28日 御命日のつどい
春には出会いと別れがあります。学校や会社などの年度がわりの時期でもあるため、別れがあり新しい出会いもあります。また、4月は釈尊の誕生月です。そして、法然上人、親鸞聖人の生まれた月でもあります。
釈尊は、釈迦族の王でありながら出家して修行をなさいました。ある意味で何の苦労もいらない環境にありながら、あえて出家の道を選びました。それは、生老病死の意味を求めるためであったと言えるでしょう。
最近、私は青木新門さんの『納棺夫日記』と映画『おくりびと』の小説を読みました。この二つの作品は、我々が人の死をどう受けとめてゆくのかということを問いかけています。
生まれたからには、やがて誰もが死を迎えなければなりません。『おくりびと』では、主人公が生活のために納棺夫という仕事に携わるなかで、多くの死者と向き合い、そこに死別の悲しみや、家族たちとの様々な出会がありました。そのなかで、戸惑いながらも自分にとって死とはどういうことなのかを考え、求め続ける姿が描かれているのでしょう。
さて、実際に死を目前にしている人と向き合うとき、どのような状況があるのでしょうか。余命数日と診断された人から、「生きている間にお経(教え)に触れておきたい」という申し出を受けたことがあります。そういう方は、たいてい病院にいます。その病院はというと、ターミナルケアに熱心なところは別としても、殆どは坊さんが正面から入っていくことは出来ません。死を目の前にした人に(物理的)に応えられない状況があるわけです。それは、僧侶イコール死を連想するからでしょう。他の患者さんが「縁起が悪い」と嫌がる訳ですよね。しかし、仏教は死者に向けられたものではなく、生きている人のために有るはずです。
『正像末和讃』には、
「五濁悪世の有情の
選択本願信ずれば 不可称不可説不可思議の
功徳は行者の身にみてり」とあります。 (真宗聖典503頁)
迷いのままに人生を全うできずに死んでゆかざるを得ない私たちに対し、本願を信じその功徳をいただくことによって生き難いこの世をいきいきと生き抜くことができる(以上、『真宗』2009年5月号より抜粋)。と教えてくれています。
また、宗教とは「人間としての仕方(しかた)」である(『同朋新聞』2009年4月号)とも言われます。生あるものの定めとしての死を考えるなかで、生老病死の迷い多きこの人生のよりどころを共に求めてまいりたいと思います。